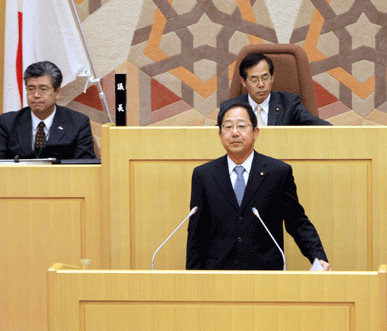平成21年3月定例会 一般質問
発 言 通 告
(1)定額給付金について
①成田市の経費および給付方法について
②給付による経済効果について
③詐欺などに遭わないセキュリティーについて
(2)後期高齢者医療制度について
①保険料の一部一律助成について
②人間ドック・脳ドックの助成について
(3)学校関係について
①学校給食について
②新設中学校計画について
③公津地区スポーツ広場について
(4)(仮称)公津の杜複合施設について
①今後の施設建設計画について
(5)さくらの山整備について
①基盤整備について
②トイレの改善について
③乗り入れ航空会社マーク表示看板設置について |
 |
 |
 |
定額給付金について3点お伺いいたします。
成田市におかれましても対象者数は約12万9千人、総給付額は約19億円を見込んでおりますが、成田市の経費・人員および給付方法についてお聞かせください。また、この給付は景気対策・経済効果等、地元の経済活性化も考えなければなりません。県内の市町村をはじめ全国でも、多くの市町村が給付時期に合わせ、市商工会とともにプレミアム付商品券を発行すると表明しています。商品券の発行は、市民の生活支援と地域の景気対策などが狙いで、地元で消費してもらうよううながし、地域経済の活性化を図ります。たとえば1万円の商品券を購入すると、1割り増しの1万1千円の買い物ができる特典です。成田市では、給付による経済効果をどのように考えているのか、また、商工会等と連携をとり商品券の発行や消費拡大のPR等の取り組みについてお聞かせください。そして給付に伴い、振り込め詐欺などの被害発生の恐れが懸念されますが、成田市では、どのようなセキュリティーを考えているかお聞かせください。 |
|
【答弁】定額給付金についてのご質問にお答えいたします。
まず、成田市の経費・人員及び給付方法についてのご質問にお答えいたします。本市が給付する定額給付金につきましては、対象者数が約12万9千人、総給付額は約19億円を見込んでおり、給付に係る事務費につきましては、現在積算をしているところですが、概ね1億円を見込んでおります。給付体制につきましては、企画課内に定額給付金班を設置し、関係課の協力のもと、給付事務を進めてまいります。給付方法につきましては、市から対象世帯主宛に申請書を送付し、対象世帯からは、必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、返送いただきます。そして、その申請書をもとに世帯主の口座に振り込む方式を基本として考えております。しかしながら、何らかの理由で申請書を記入することができない世帯、また、振込口座をお持ちでない世帯も想定されますので、窓口での申請受理、現金渡し等も検討してまいります。
次に、定額給付金の配布による経済効果をどのように考えているかとのご質問ですが、内閣府によりますと、平成20年12月19日に出された政府経済見通しを作成するに当たっては、定額給付金の約4割が消費に回ると想定し、実質成長率を0.2パーセント分押し上げると試算したとのことです。成田市については、市民への定額給付金給付額が約19億円ですので、そのうちの4割が消費に回った場合、約7億6千万円の経済効果があることとなります。次に、商品券の発行や消費拡大のPRなどの取り組みについてのご質問ですが、いわゆるプレミアム付き商品券の発行につきましては、より経済効果が見込まれることから、現在商工団体において、実施に向けた調整が行われておるところですが、実施となれば市といたしましても支援してまいりたいと考えております。また、消費の拡大についても商工団体と連携をしながらPRをしていきたいと思います。次に、詐欺などに遭わないセキュリティーについてのご質問にお答えいたします。定額給付金の給付を装った振り込め詐欺や個人情報搾取につきましては、広報なりたや市のホームページにより注意を促しているところです。また、発送・返送の際の郵送方法の検討や、申請内容の確認等で市から対象世帯に連絡する方法についても検討し、対象世帯に確実に申請書類が届き、対象者が不安を抱かないような仕組みづくりに努めてまいりたいと考えております。
|
後期高齢者医療制度についてお伺いいたします。
後期高齢者医療制度の運営は千葉県全56市町村で構成される「広域連合」が行なっており、保険料の決定や医療の給付などは広域連合が行い、各種申請や届出の受付、保険料の徴収は市で行なっております。保険料は、被保険者の前年の所得を基にして計算し、原則として住んでいる市町村を問わず、県内均一となり、平成20年度と21年度の2ヵ年間は同額の保険料となりますが、成田市には被保険者数はどれくらいいるのかお聞かせください。また、厚生労働省は(長寿)後期医療制度の創設により、現役並み所得者の判定基準について、同一の世帯に属する被保険者のみの所得および収入をもとに判定することとしたことに伴い、一部に現役並み所得者に移行する方が生じたため、平成21年1月から一部改正されました。対象者はどれくらいの方がおられたのかお聞かせください。この制度の運営は広域連合が行っておりますが、広域連合より厚生労働省に対して、電算システム全体の抜本的改善等強く要望していますが、どのような不具合、被保険者に対しての損害等はあったのかまた、市町村負担金の余剰金は返還されるのか、お聞かせください。そして、この制度は、市町村が独自に保険料自体を軽減できない仕組みのため、見合い分を支給する形をとっている市町村もあります。成田市におかれましても、保険料の一部を一律助成はできないものかお聞かせください。 |
|
【答弁】後期高齢者医療制度についてのご質問にお答えいたします。
まず、後期高齢者医療被保険者数につきましては、平成20年12月末現在で9, 622人です。続きまして、本年1月から一部改正された医療費の自己負担割合でありますが、住民税課税所得や収入額において、一定の条件を充たした場合は、申請により自己負担割合が3割負担から1割負担となることに改正されたものであります。当市においては、 10人の方が該当し、その方々に文書の送付や窓口での説明を行い、変更後の被保険者証をすでに交付しております。
続きまして、千葉県後期高齢者医療広域連合による厚生労働省への電算システムの改善要望についてですが、広域連合に確認いたしましたところ、高額療養費の算定にあたり、システムに不具合が生じて、算定事務が遅れているとのことであり、被保険者の方々にご迷惑をおかけしたところでありますが、現在出来るだけ早く、給付が行えるよう努力しているところであります、との報告を受けております。続きまして、千葉県後期高齢者医療広域連合市町村負担金の剰余金としての返還でありますが、決算剰余金の取扱は、制度がスタートして間もないことから、今後の運営安定化を図る必要があり、広域連合において基金に積み立てをするため、返還はございません。
次に、被保険者に対する保険料の一律助成についてのご質問ですが、保険料は被保険者の負担能力に応じて公平に負担していただくことになっており、また、保険料の軽減策も図られていることから、保険料のあり方については、保険者である広域連合を中心に参加市町村全体で検討されることが望ましいと考えますので、ご理解をお願いいたします。
|
人間ドック・脳ドックの助成についてお伺いします。
健康維持と病気の早期発見につながる人間ドックも年齢で差別する後期高齢者医療制度の問題点が浮き彫りになっております。人間ドックへの助成は市町村が運営する国民健康保険がそれぞれ行い、国保加入者のドック受診費用の一部を補助する仕組みです。成田市でも75歳以上の方を対象にしていましたが平成19年度国保で75歳以上の人間ドック等の助成を受けられた方はどれくらいいるのかお聞かせください。そして、平成20年度からは、全国582市区町村が75歳以上への助成を廃止。引き続き実施する市区町村は141へと激減しました。廃止した市町村の多くは、75歳以上が国保から脱退させられ、後期高齢者医療制度に移行したための措置とみられます。厚生労働省は「助成を継続するか、しないかは自治体の判断」としていますが、平成20年4月以降も保健センターなどの事業として助成を継続しているのは141市区町村が実施しています。成田市でも、人間ドックおよび脳ドックの助成をできないか考えをお聞かせください。 |
| 【答弁】次に、人間ドック・脳ドックの助成についてですが、平成19年度実績で、国民健康保険の被保険者75歳以上の人間ドック受診者は、30人となっております。平成20年4月より後期高齢者医療制度が創設され、 75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となり、それまで国保の被保険者として人間ドックを受検されていた方は助成の対象外となりました。現状においては、 75歳未満の国保被保険者と同様に無料で健診ができる後期高齢者健康診査事業をご利用いただいております。ご質問の人間ドック助成事業につきましては、保険者である広域連合が実施することが望ましいと考えますが、広域連合では当該事業を実施するのは困難であるとの方針が示されておりますので、今後は、市として人間ドック及び脳ドック助成について、強い前向きで検討してまいりたいと考えております。
|
学校関係についてお伺いいたします。
児童・生徒に栄養的にバランスのとれた食物を摂取させることにより、心身の健全な発達を図ることを目的として、学校で集団的に行われる食事また、食事作法の指導なども、学校の教育課程のなかに組み入れて実施しています。また、食物アレルギーの児童生徒も安心して食べられる学校給食の提供が必要とされております。教育民生常任委員会では、2月5日に佐倉市にあります染井野小学校の学校給食の自校方式および食育について視察して参りました。佐倉市では、すべての小・中学校が自校方式の給食を実施しており、心のこもったきめ細かな給食を実施しております。また、各学校が食材として地元農産物を利用し、生産者の顔が見える安全でおいしい給食づくりに心がけており、献立を生きた教材として使い、食育の推進にも取り組んでおります。議場におられます皆様に、配布させていただきましたが、これは、当日の献立を大きくしたものです。この日のメニューは、(ゆかりごはん・牛乳・佐倉豚とサトイモの煮物・にんじんサラダ・手作りオレンジゼリー)ひとことメモ・・今日は、佐倉市弥富地区で熱田さんが育てた佐倉豚と同じく佐倉市でとれたサトイモを山形県の郷土料理・芋煮風に煮ました。また、にんじんも佐倉市でとれたもので、染井野小人気メニューの1つにんじんサラダにしました。このような献立を毎日給食時に出しているとのことです。・・献立ひとつにしても心がこもっております。また、給食費は各学校の校長が保護者から徴収する |
 |
システムになっており、平成19年度の未納金額は401万円で169人、0.6%と大変少ないです。教育民生常任委員会に同行し視察に行きました染井野小学校の感想、そして学校給食センター運営委員会での中学校デリバリー方式での視察の感想をお聞かせください。また、玉造給食センターの老朽化などで、様々な検討をしなければならない時期に来ております。給食施設計画はどのように検討し考えているのか、そして今後新設校等での自校方式の考え等もありましたらお聞かせください。 |
【答弁】学校給食についてのご質問にお答えいたします。
まず、佐倉市の自校給食及び川崎市のデリバリー給食の感想ですが、職員より次のように報告を受けております。佐倉市染井野小学校の給食を試食しての第一印象は「自校給食の味は家庭料理の味」。家庭ではなかなか増やせない料理のバリエーションが学校給食によって多彩に展開できていると感じました。また、学校給食が「食育」として確かに機能しており、栄養士が毎日子ども達の食事の様子を見て、その状況から次の献立や調理を工夫しようとするサイクルが確立されていましたも子どもたちも、学校に調理室があることで食に対する関心が高まり、作ってくれる方々に感謝したり、自らも食材となる野菜を育てたりすることによってさらに食育が推進されていくのではないかと感じました。との報告でした。続きまして、成田市学校給食センター運営委員会におきまして、本年2月5日、デリバリー方式を採用している川崎市の中学校及び受託業者の調理場視察の報告ですが、川崎市は、 16年度から市内51校すべてで献立に対する指導以外の全業務を業者委託しており、アレルギー対策については、業者と保護者の間でアレルゲンの確認を行なっています。本格実施から5年が経過しようとしている現在、試行開始当初50パーセントの予約率があったデリバリー弁当も、 16年度には10パーセントに、現在は2パーセント強にまで下がっており、予約率の向上に苦慮しているということです。これに伴い、当日の朝の予約を可能にしたことや、ウエブによる予約も導入しましたが歯止めがかからず、業者が撤退する危険性もあるということです。なお、業者の調理場は、コンパクトにまとめられ、手際よく作業できると思われ、また保健所の検査も通っているとのことで、衛生管理も行き届いているとの印象を受けました。視察後の感想としては、デリバリーを導入する場合は、まず保護者の理解が最優先であり、衛生管理の行き届いた調理場を保有する業者の確保など、課題があると感じました。以上のような報告でございます。私といたしましては、今回は1市のみの視察ですので、現時点では成田市になじむのかどうかの判断は難しいと思います。今後とも、自校方式の学校、あるいはセンターの視察など、成田市の児童・生徒にとってどのような方式がよいのか、研究して参りたいと考えております。
次に、給食施設計画の検討についてですが、学校給食センター本所及び玉造分所は経年による老朽化が著しいため、新たな施設整備の検討する時期にきており、新年度予算に基本計画の策定に要する経費を計上させていただいております。この基本計画の策定に当たっては、学校適正配置案も踏まえ、今後の学校給食のあり方について検討をしてまいります。その中で、センター方式、自校方式の比較検討をするとともに、食育の観点から地産地消の推進、デリバリー給食、食物アレルギーヘの対応策など、様々な角度から検討してまいりたいと考えております。 |
|
新設中学校建設の計画について
西中学校は平成21年1月現在、生徒数は760人で、平成25年度では約994名と毎年生徒数が増加し、教室の不足で
|
 |
公津地区におけるスポーツ広場についてお伺いいたします。
学校予定地では現在、公津スポーツ広場として少年野球チーム等が使用しておりますが、あくまでも暫定的であります。台方・船形地先のニュータウン地区スポーツ広場近接地に公津スポーツ広場の計画がありますが、用地確保が難しいと聞いておりますが、 |
|
今月より仮設校舎、4教室増で対応しています。学校規模の適正化、通学区域の再編等があり、大規模校化に対処するため西中学校分離新設校を公津の杜地区に建設を予定しています。新設中学校建設の具体的な計画についてお聞かせください。
|
 |
スポーツ広場の当初の計画および今後の計画についてお聞かせください。 |
|
【答弁】新設中学校建設の計画および公津地区におけるスポーツ広場についてのご質問にお答えいたします。
まず、新設中学校建設の具体的な計画についてのご質問でありますが、西中学校分離新設校につきましては、昨年3月に報告させて頂きました「学校適正配置案」に基づき、既に用地が確保されている公津の社地区に平成25年度の開校を目途に、平成21年度に基本設計を、22年度に実施設計を行い、23年度から2ヵ年をかけて建設する計画でおります。
次に、スポーツ広場の当初の計画および今後の計画についてのご質問でありますが、公津スポーツ広場につきましては、公津地区青少年健全育成協議会外4団体から平成19年9月に、台方・船形地先の成田ニュータウン地区スポーツ広場の近接地に設置して欲しい旨の要望書が提出され、要望の主旨を踏まえ、計画を進める旨の回答をしたところであります。このようなことから、平成20年度に基本設計、測量・物件調査、21年度に実施設計、 22年度から23年度にかけて用地買収及び本工事を進める計画でありましたが、現在、用地については、難しい状況になっておりますので新たな候補地を調査しているところであります。従いまして、スケジュール的には、当初の見込みから多少の遅れは考えられますが、スポーツ広場の整備につきましては、喫緊の課題として認識しておりますので、候補地を早期に選定し、整備について最大限の努力をしてまいりますので、ご理解をお願いいたします。
|
(仮称)公津の杜複合施設建設計画についてお伺いいたします。
成田市では、市民の皆様のコミュニティ活動をサポートする拠点として、コミュニティセンターの整備を推進しています。しかし、成田国際文化会館の建て替えおよび市民の多くの方々が利用しています中央公民館の老朽化、赤坂センター地区の土地利用計画との整合を図るため、施設計画及び事業手法の再検討を行っています。(仮称)公津の杜複合施設整備事業における、今後の施設建設計画についてお聞かせください。 |
 |
|
【答弁】(仮称)公津の杜複合施設整備事業における、今後の施設建設計画についてのご質問にお答えいたします。
(仮称)公津の杜複合施設につきましては、「コミュニティと文化の複合拠点」とのコンセプトを掲げ、図書館及び子育て支援施設等を備えるコミュニティセンターと小規模の文化ホールを擁する複合施設として、これまで計画を進めてまいりました。しかしながら、国際文化会館の全面改修や赤坂センター地区土地利用等、本事業を取り巻く状況が著しく変化したことを受けて、現在、当初計画の見直し作業を行っているところでございます。計画見直しの方針と致しましては、21年度の施政方針でも申し上げたところでございますが、よリコミュニティに重点を置き、市民の自主的活動や世代を超えた交流の場を提供し、コミュニティの醸成、促進に寄与する施設にしてまいりたいと考えております。これまで様々ご議論のありました文化ホールにつきましては、今後の計画に委ねることとし、これに代わるものとして、本施設計画では、図書館、市民ギャラリー等の拡充を検討しております。なお、新年度当初予算に「公津の杜複合施設基本設計委託料」を計上させていただいておりますので、よろしくご理解とご協力をお願い申し上げます。
|
さくらの山整備についてお伺いいたします。
成田市さくらの山は、成田空港に隣接する駒井野地先の小高い丘に位置し、さくらの木の下で航空機の離発着の素晴らしい眺めが望めます。テレビ等の撮影で使われるなど成田の新たな観光スポットとなっており、また、ちば眺望100景にも選ばれております。21年度予算では、さくらの山整備事業で1,290万円が計上され、観光名所としての基盤整備を行うとありますが、どのような内容かお聞かせください。また、桜の花の時季やゴールデンウィークなど、多くの方々が訪れますが、現状のトイレで対応できるのか、改善はどのように考えているのかお聞かせください。そして多くの方々が離発着する飛行機を見にこられております。特に子供たちがどこの飛行機かわかるように、空港に乗り入れている航空会社のマーク表示看板を設置していただきたいと思いますがいかがでしょうかお聞かせください。以上で1回目の質問を終わります。
※詳しくは、成田市議会議事録をご覧ください。
|
|
【答弁】さくらの山整備についてのご質問にお答えいたします。
まず、観光名所の基盤整備についてというご質問でございますが、さくらの山は雑誌などでも数多く紹介され、今や年間25万人以上が訪れる市内有数の人気観光スポットとなっております。昨年、 3月~5月に実施した調査では、利用者の約7割が市外の方で、改めて重要な観光拠点と認識したところでございます。市では、これまでにもトイレの設置や駐車場の拡張、地場産品販売のための条例改正などの整備を進めてまいりましたが、さらに敷地内の約2ヘクタールの未利用地を整備することにより、利用客の利便向上を図りたいと考えております。そこで、来年度は、さくらの山景観保全整備工事として駐車場と京成線に挟まれた未利用の雑木林の間伐を行い、園路整備や山桜・ツツジなどの植栽を実施する予定でございます。
次に、現状のトイレの改善についてお答えいたします。現在のトイレにつきましては、通常の利用ではほとんど問題はありませんが、桜の花の時季やゴールデンウィークといった利用者の集中するようなときに長い行列ができるなど、大変ご不便をお掛けしております。今後も利用者の増加が見込まれることから、新たなトイレ設置について検討しているところでございますが、当面の混雑時対応といたしまして、環境に配慮したリサイクル式簡易トイレを設置する予定でございます。
最後に、乗り入れ航空会社のマーク表示看板を設置してはどうか、というご質問でございますが、さくらの山を利用する多くの人、特に子どもたちの見学の楽しみを増やすだけでなく、学習面でも役立つ試みであると思いますので、成田国際空港株式会社と連携を取りながら設置に向け取り組んでまいりたいと考えております。また、パンフレット等による同様のサービスも考えられますので、これらの方法についても検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
|